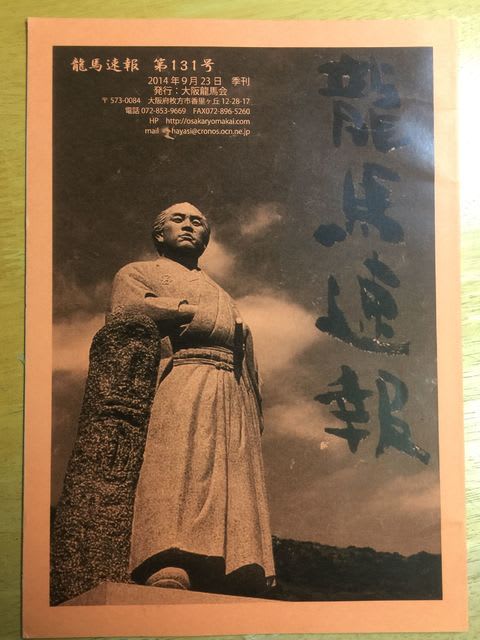長谷吉治幹事の案内で守口宿へ
余談から入ります。京街道シリーズは本当なら京都から大阪まで歩くつもりでした。第1弾は鳥羽から淀、第2弾は淀から八幡、第3弾は八幡から楠葉と順調に歩いておりました。が、楠葉から枚方宿までほとんど住宅地。ひたすら歩くだけになってしまう。そこで全行程を歩くのは断念して要所要所を押さえようと、第4弾は枚方宿、そしてこの第5弾は守口宿となりました。京街道には橋本・枚方・守口に宿があったので、これで良しと一人で納得しました。起点というか終点の高麗橋付近は長谷さんのイベントで案内されているのでまあいいかです。
1 江戸川乱歩寓居跡
地下鉄守口駅に江戸川乱歩寓居跡の看板を見たことがありました。劇団潮流で「夢幻乱歩館」を上演するとき、江戸川乱歩について少しは勉強しました。守口に住んでいたことも知ってはいましたが・・・。テキストに「推理小説家江戸川乱歩が27歳の頃、父を頼り、守口市、門真市を転々と5回移り住んだ・・・。」えっ!5回も。確かに引っ越し魔とは知っていましたが。
さて、長谷吉治講師から「たまには史跡を皆さんで探してみませんか」と言われ、参加者は必死に探す。探す史跡は「名探偵明智小五郎が初めて登場するD坂の殺人事件執筆地」。写真も住所もわかるので楽勝かと思われましたがなかなか見つからず・・・。しまいにはU田氏は通りすがりの美魔女に声をかける有様。残念ながらタイムオーバー。案内されたのはマンションン1階のベランダ。のぞき行為に近い恰好で見ましたが、これは見つからへんわ。
![]()
さあ、クイズの時間です。この写真の史跡を探してくださいと江戸川乱歩寓居跡をさがす
![]()
マンションのベランダを覗き込むと見える石版
2東海道(京街道)一里塚跡
東海道は日本橋からスタートし、最初の宿場である品川から57番目の宿場が守口で、最終地点は高麗橋東詰になる。守口宿の東端に該当する箇所が、たまたま一里に該当し、一里塚が置かれた。こんなところにあるのかと驚き、しっかり保存されていたのはうれしい。守口の一里塚跡は西側に碑が残ってます。
![]()
3 明治天皇行在所の難宗寺
『大きなお寺で、蓮如上人が文明9年に創建したと伝えられる。慶応4年3月21日、明治天皇は大坂へ行幸する途中、難宗寺を宿所とした。翌日、出発された天皇は大阪の西本願寺津村別院(北御堂)に到着し、44日間滞在された。
難宗寺には明治天皇の御座所が今でも保存されている。この行幸に随行した人数が1659名だった。随行者の宿所は佐太(守口市)から関目(大阪市旭区)までの広範囲にわたり宿が割り当てられた。
明治43年10月3日、当時の皇太子(のちの大正天皇)も宿泊されている。
また、境内には大阪府の天然物指定されている銀杏の大木がある。』いや、びっくり。行在所が守口にあるなんて。そのまま残ってるし。長谷講師に感謝しながら拝見。写真撮影もできたからうれしさ倍増。
明治天皇行在所。写真左下の木製箱は大正天皇使用の湯殿(お風呂)。貴重やわ。
守口宿本陣では、宿場の勉強。3月の正井さんのお話でも宿場の勉強しました。
4 桂小五郎宿泊の地
小五郎は守口にも来ていたのか。
『駒井正三著の「ふる里守口を訪ねて(発行 守口市市長室広報担当)」によると、幕末期、長州藩士桂小五郎(木戸孝允)は、大坂に用事があってもできるだけ大坂で宿泊せず、守口に宿泊したとの記載がある。
桂が宿泊したゆかりの地が呉服商茜屋であった。茜屋のご子孫である西田家には、桂が書き記した書が所蔵されていた。(現在は、代が変わり、西田寛三氏の御子息にお聞きしたところ、桂が書き記した書は、行方不明だとの事である。)
桂は守口や森小路に宿泊したと言い伝えられている。』
![]()
司馬遼太郎住居跡も行きました。司馬さんは守口に住んでいたのか。西区のマンションしか知らなかったし、「梟の城」を書いたのもここと聞いてビックリ。
![]()
文禄堤を歩き次の案内場所へ。
5 第14代将軍徳川家茂宿泊の地
守口宿とお別れして大阪市内へ京街道を進む。
『文久3年(1863)3月、第14代将軍徳川家茂は、第3代将軍徳川家光以来、230年振りに上京した。
この時、家茂は朝議で攘夷実行期限を五月十日」と約束させられる。
家茂は、4月23日に大坂城へ入城した。大坂城へ将軍が登城するのも家光以来のことだった。
家茂は5月11日まで大阪に滞在したが、その期間中に宿泊したと伝えられるのが「木犀の陣屋」である。時期は、文久3年4月と伝わっている。
この陣屋とは、庄屋の浅田家の屋敷で、庭に木犀の木が三本あり、これらの木から醸し出す香りが、遠くまで漂っていたことから「木犀の陣屋」と呼ばれていた。
しかし、「徳川實記」で見る限り、家茂が大坂城以外で宿泊したのは、岸和田にて順動丸で碇泊した4月28日以外は記載がない。
唯一、4月26日に大坂城から離れて、数か所の新田会所を訪れている。その時にここを訪れて小休止したのが宿泊に誤って伝えられたものかもしれない。また、その後、家茂は2回、大坂城へ入城し、最終的には大坂城内で亡くなった。』
![]()
![]()
記念撮影
![]()
![]()